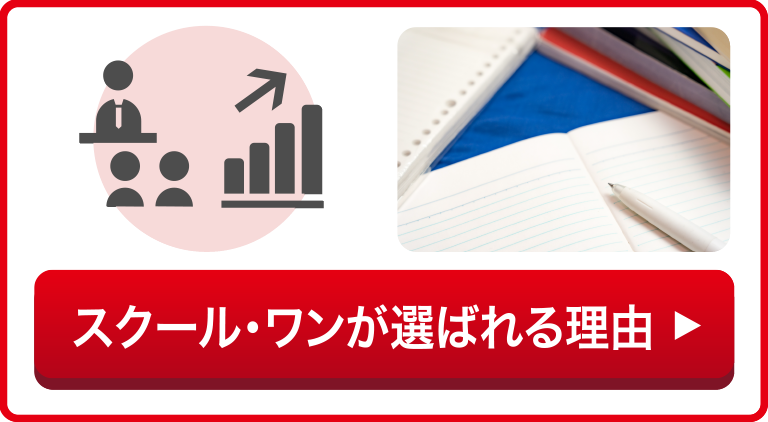次の学習指導要領改訂へ
2024.12.27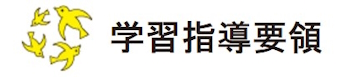
小中学校や高校の教育目標や内容を定めた学習指導要領について、阿部文部科学大臣は、次の改訂に向けた検討を、今冬にも中教審=中央教育審議会に諮問したいという意向を示しました。
そもそも「学習指導要領」とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準です。およそ10年に1度、改訂しています。子どもたちの教科書や時間割は、これを基に作られています。
現行の学習指導要領は、小学校では2020年度(令和2年度)、中学校では2021年度(令和3年度)、高等学校では2022年度(令和4年度)の新入生から全面実施されていますが、早くも次の学習指導要領改訂に向けた動きが始まろうとしています。
具体的には今冬の諮問を受け、中教審の答申が2026年内に出される運びとなり、そこからは間を置かず改訂→移行→実施と進んでいきます。前回の改定の記憶も新しいですが、今一度これまでのトピックスについて振り返ってみましょう。
○1989(平成元)年改訂
生活科を小学校1・2年で導入
高等学校家庭科の男女必修化
○1998・99(平成10・11)年改訂
総合的な学習の時間を導入
情報科を高等学校で導入
○2008・09(平成20・21)年改訂
外国語活動を小学校5・6年で導入
○2015(平成27)年一部改正
道徳の「特別の教科」化
〇2017・18年(平成29・30)年改訂
「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現
(※)「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」
(「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の視点からの授業改善、カリキュラム・マネジメントの推進、小学校外国語科の新設等)
学習指導要領の改訂がなぜ行われるかは、学校が社会と切り離された存在ではなく、社会の中にあるためです。グローバル化や急速な情報化、技術革新など、社会の変化を見据えて、子供たちがこれから生きていくために必要な資質や能力について見直しを行う必要があるためなのです。

さて、現代で起きている事象にはどのようなものがあるでしょうか。不登校児童生徒の増加・外国人児童生徒の増加・子供の体力の低下傾向・読書離れ・生成AIとの付き合い方・多様化への対応、等々本当に多くの事柄が教育を取り巻く環境で起こっています。果たして次の学習指導要領で子どもたちにどのような力を育もうとするのでしょうか。
今後の中教審の答申を注意深く見ていきたいと思います。
本部としてはこのような変化に対して情報を収集し、加盟店の皆様にも安心して生徒指導のお役に立てるよう備えております。次代を担う子どもたちへの教育・人づくりがやりがいに繋がる京進の個別指導 スクール・ワンの運営に興味のある方は、ぜひご連絡ください。
お待ちしております。
東日本ブロック 遠藤
★FCオーナー募集個別相談会は住所入力不要! 資料請求も随時受付中です!
FC教室長経験後に独立する選択肢もありますので、お気軽にお問い合わせください。
資料請求⇒https://fcs1.kyoshin.jp/contactform
個別相談⇒https://fcs1.kyoshin.jp/entryform